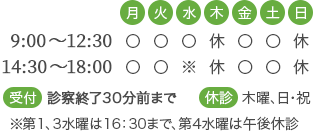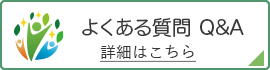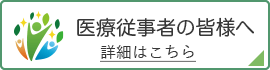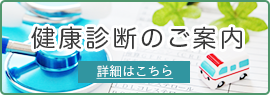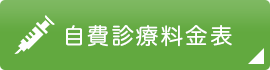血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。
脂質の異常には、LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(いわゆる善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度の異常があります。
これらはいずれも、動脈硬化の促進と関連します。
脂質異常症には、大きく分けて血液中の脂質濃度が基準の値よりも高い「高脂血症」と、基準の値より低い「低脂血症」があります。
また、原因別に分けると、原発性脂質異常症と他の疾患(肥満、糖尿病、腎疾患、内分泌疾患、肝疾患など)や薬剤使用に基づいて起こる続発性脂質異常症があります。
脂質異常症の診断基準
LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドのうち、メタボリックシンドロームの診断基準に用いられる脂質の指標は、HDLコレステロールとトリグリセライドです。
しかし、LDLコレステロールは単独でも強力に動脈硬化を進行させるため、メタボリックシンドロームの有無に関係なく、LDLコレステロールの値にも注意する必要があります。
脂質異常症の診断基準は以下の図表のとおりですが、この基準に当てはまる場合でも、すぐに治療が必要というわけではありません。
脂質異常症診断基準(空腹時採血)

*10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。
*スクリーニングで境界域高LDLコレステロール血症、境界域高non-HDLコレステロール血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し治療の必要性を考慮する。
(厚生労働省 「生活習慣病予防のための健康情報サイト」より引用)
脂質異常症の原因と改善方法
原因
LDLコレステロールの高値の原因として、第一に食事中の飽和脂肪酸の摂り過ぎがあげられます。
飽和脂肪酸は、肉の脂身(赤身ではなく白い部分。バラ肉、ひき肉、鶏肉の皮も含む。)・バターやラード・生クリームなどに多く含まれます。
インスタントラーメンなど加工食品にも含まれています。
一般的には、冷蔵庫の中で固まっている油脂は、飽和脂肪酸の多い油脂であることが多く、サラダ油や魚油のような液体の油は、不飽和脂肪酸の多い油脂であることが多くなっています。
また、食事中のコレステロールもLDLコレステロールを高くしますが、個人差が大きく、飽和脂肪酸と比べると影響が小さいことが知られています。
食事中のコレステロールは、主に鶏卵の黄身や魚卵から摂取されます。
改善方法
LDLコレステロールが高い人で、飽和脂肪酸やコレステロールを食べる量が非常に多い人は、その量を控えることで、比較的容易にLDLコレステロールを下げることができます。
現時点では、LDLコレステロールが高い人が注意すべきことは、まず飽和脂肪酸であり、次いで鶏卵などコレステロールの多い食品についても食べすぎないようにすることが勧められます。
トリグリセライド(中性脂肪)の高値の要因としては、エネルギー量のとりすぎ、特に甘いものやアルコール・油もの・糖質のとりすぎがあげられます。
砂糖の入ったソフトドリンクを飲む習慣のある人も多い傾向があります。
これらを改めて運動や減量を行うことで、中性脂肪を下げることができます。
また背の青い魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸にはトリグリセライド(中性脂肪)を下げる働きがあります。
HDLコレステロールの低値はトリグリセライド(中性脂肪)の高値と連動することが多く、その要因は、肥満や喫煙・運動不足です。
運動や減量・禁煙によりHDLコレステロールの上昇が見込まれます。
また飲酒には、HDLコレステロールを高くする働きがありますが、飲酒は1合からでも高血圧や肝障害を悪化させますので、HDLコレステロールを上昇させるために飲酒を勧めることはできません。
健康診断などでコレステロールの値で異常値であった場合など、つくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックまでお気軽にご相談ください。
脂質異常症を改善するための運動
脂質異常症の治療は、生活習慣の改善が根幹であり、安易な薬物療法は慎み、薬物療法中も生活習慣の改善を行うべきとされています。
運動療法として、中強度以上の有酸素運動を中心に定期的に(毎日合計30分以上を目標に)行うことが推奨されています。
運動療法により血中脂質の改善効果が得られ、脂質異常症を改善します。
運動療法は脂質異常症患者だけでなく健常者において、トリグリセライドを低下、HDLコレステロールを増大させ、血中脂質値に好影響を及ぼします。
「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド2018年版」では、以下のような運動種目・時間・頻度・強度の運動療法を推奨しています。
- 運動種目
有酸素運動を中心とした種目として、ウォーキング、速歩、水泳、スロージョギング(歩くような速さのジョギング)、自転車、ベンチステップ運動などの大きな筋をダイナミックに動かす身体活動。 - 運動時間・頻度
1日の合計30分以上の運動を毎日続けることが望ましい(少なくとも週3日は実施すること)。
また、1日の中で短時間の運動を数回に分けて合計して30分以上としてもよい(例:10分間の運動を3回実施で合計30分間)。 - 運動強度
中強度以上の運動を推奨する。中強度以上の運動とは3メッツ以上の強度であり、通常速度のウォーキングに相当する強度の運動である。
そのため、通常の歩行あるいはそれ以上の強度での運動が推奨されるが、心血管疾患や骨関節疾患がある場合や低体力者の場合には、急に運動を実施することは身体に与える負担が大きいため、3メッツ以下の強度の身体活動である、掃除、洗車、子供と遊ぶ、自転車で買い物に行くなどの生活活動のなかで身体活動量を増やすことからはじめてもよい。
血中脂質値は1回の運動では影響を受けません。
そのため血中脂質値に好影響を与えるには数ヶ月以上の長期的な運動療法が必要となります。
有酸素運動が血中脂質レベルを改善させる機序として、筋のリポプロテインリパーゼ活性が増大し、トリアシルグリセロール(血中カイロミクロン・VLDL・LDL)の分解を促進させることにより、HDLを増やすことが関与していると考えられています。
HDLは「善玉コレステロール」として知られていますが、末梢組織や細胞から余剰なコレステロールを回収し、肝臓に運搬する役割を有しています。
つまりHDLコレステロールは脂質異常症の進展を抑制する働きがあります。
運動を実施する上での注意点
準備・整理運動を十分に行うこと、メディカルチェックを受けて狭心症や心筋梗塞などの心血管合併症の有無を確認し、運動療法の可否を確認した後に、個人の基礎体力・年齢・体重・健康状態などを踏まえて運動量を設定する必要があります。
脂質異常症の改善には運動療法だけでなく、食塩摂取量やアルコール摂取量の制限、禁煙などとの併用療法がより効果的といえます。

つくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。
つくば市のB-leafメディカル内科小児科クリニックはバス停「小野崎南」より徒歩5分。
ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でもお気軽にご相談ください。
参考文献
この記事の監修者
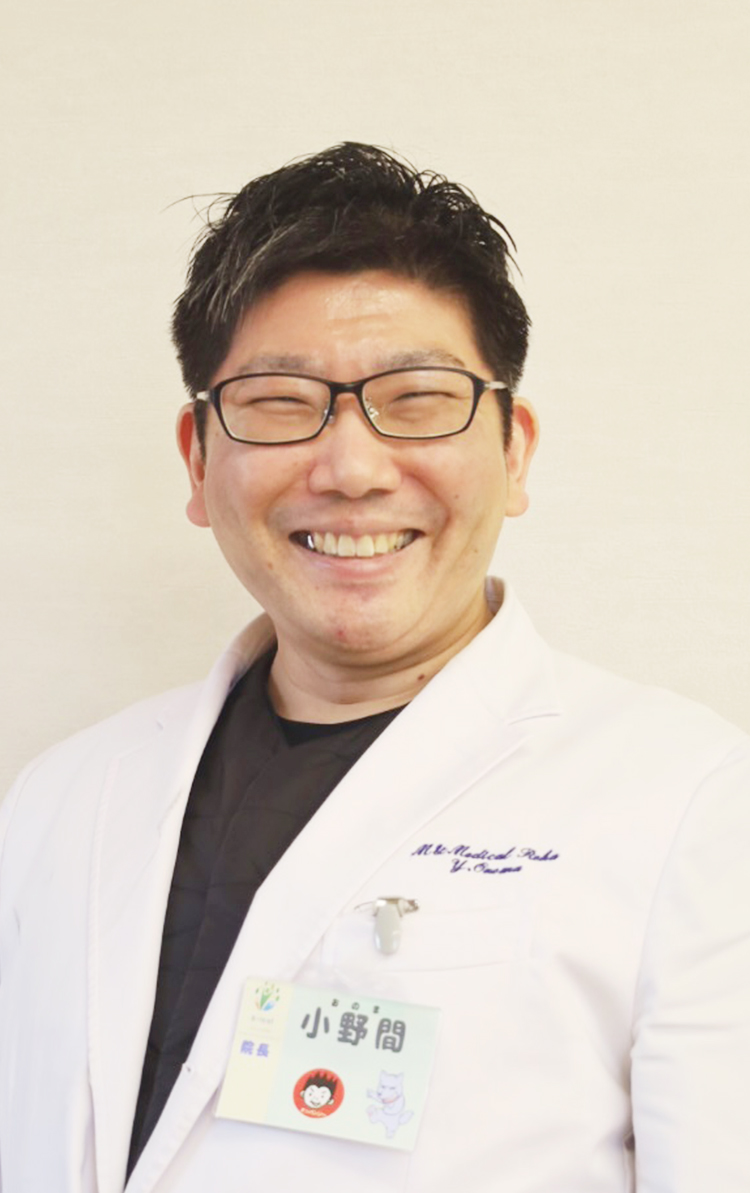
小野間 優介(おのま ゆうすけ)
B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長
- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得
- 日本医師会認定産業医
- 茨城県難病指定医
- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
--プロフィール--
2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、
『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』
『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』
をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。
関連リンク
- 病名から探す
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症

- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症