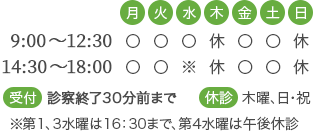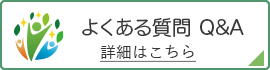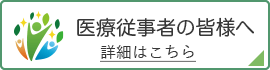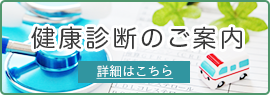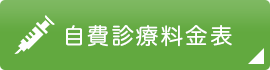のどの痛みのことを一般的に“咽頭痛(いんとうつう)”といいます。
ときに痛みが強く、食事もとりづらくなってしまう咽頭痛。
では、咽頭痛はなぜ起こるのでしょうか?
咽頭痛について知っておきたいことを、わかりやすく解説します。
咽頭痛とは
咽頭痛とは、炎症や外傷・病気などでのどに炎症を起こし痛みが生じる病気です。
咽頭痛がひどくなると唾液を飲み込むこともつらくなり、ときに食事も満足にできなくなるケースがあります。
ほとんどの咽頭痛は風邪をひき(風邪ウイルスに感染し)、のどや扁桃腺が炎症を起こして腫れたことが原因で起こります。
そのため、のどや扁桃腺の炎症が治まれば次第に症状は改善します。
しかしながら、なかには以下のような原因もあり、一概に風邪のせいだから大丈夫とは言い切れないのが咽頭痛の気をつけなければならないポイントです。
| 傷や異物 | 何かが刺さったり引っかかったりして、のどに傷ができる 例)魚の骨、箸、薬のシート |
|---|---|
| 腫瘍 | がんなどの腫瘍 |
| 神経の病気 | のどの周りにある舌咽神経の病気 |
| アルコール | 高すぎるアルコール度数のお酒はのどの粘膜を傷つけることがある |
| そのほか | 狭心症や心筋梗塞の放散痛 |
咽頭痛の症状
咽頭痛の代表的な症状は、以下のとおりです。
- のどがヒリヒリ痛む
- 焼けるような痛み
- 何をしなくてものどが痛む
- 唾液を飲み込むと痛む
- ビリビリとしびれるような痛み
症状の程度には個人差が大きいのが咽頭痛の特徴です。
風邪などによる喉の炎症(急性咽頭炎)が原因であれば、数日から1週間程度で症状の改善が期待できます。
気になる症状があれば、お近くの内科を受診しましょう。
またつくば市の内科B-leafメディカル内科小児科クリニックでも咽頭痛の治療を行っています。
お気軽にご相談ください。
咽頭痛の検査
咽頭痛の原因を明らかにするために、まずは問診や口の中を目で見る視診をおこないます。
一般的な咽頭炎と少し異なる様子が疑われる場合には、頸部のレントゲン検査やCT検査などをおこなう場合もあります。
なかには鼻から細いチューブを通して、より詳細に咽頭を観察するファイバースコープ検査をおこなう場合もあります。
この際に使用されるファイバースコープは胃カメラよりも細いため、痛みや苦痛はかなり少なくなっています。
咽頭痛の治療
咽頭痛の治療方法は、原因によって異なります。順に解説します。
1)のどの炎症
急性咽頭炎などのどの一時的な炎症が原因の方は、次のような薬を服用し症状の改善を期待します。
- 抗生物質
- 炎症を抑える薬
- 痛み止め
- ステロイド薬
さらにのどの炎症がはやく改善するように、次の対策を取り入れるのもおすすめです。
- よく眠る
- 栄養がありのどに優しいものを食べる
- 水分をしっかりとる
- 身体を冷やさないようにする
- マスクをして加湿する
- (水で)うがいをする(炎症が起きている時はうがい薬の使用はお控えください)
2)傷や異物
傷や異物などが原因で咽頭痛が起こっている方は、異物がのどに引っかかっていれば除去します。
多くの場合は、自然に傷が治り咽頭痛が軽減するのを待ちます。
3)腫瘍
腫瘍ができている方は、まずは組織の一部を採取し“がん”か“がん以外の腫瘍”かを診断します。
がんと診断されたら、手術による切除や抗がん剤治療・放射線治療などをおこないます。
がん以外の腫瘍の場合は、手術による切除をおこないます。
4)神経の病気
神経の興奮を抑える薬を服用し、症状の改善を期待します。
咽頭痛で受診するときに
医師に伝えていただきたい5つのポイント
咽頭痛の原因を突き止めるためには、患者さんからの情報が重要です。
ここからは、咽頭痛で受診するときに医師に伝えていただきたい5つのポイントをまとめました。
1)いつから痛むのか
急にのどが痛くなったのか、数日間もしくは数か月続いているのかをお伝えください。
2)どのようなときに痛むのか
何もしなくても痛むのか、食事など塊を飲み込んだときに痛むのか、唾液を飲み込んでも痛いのかをお伝えください。
3)咽頭痛が起こったきっかけはあるか
のどに魚の骨が刺さったり、高い度数のアルコールを飲んだりなど、咽頭痛が起こるきっかけに心当たりがある方はお伝えください。
4)のどの痛み以外に気になる症状
咽頭痛の原因は風邪など、のどの感染症の場合が多いです。
熱や咳、痰、下痢や腹痛などのどの痛み以外に気になる症状がありましたらお伝えください。
5)今までかかった病気
今までかかった病気についての情報はとても重要です。
心臓病やがんなどの大きな病気から、健康診断で指摘されたものまで、なんでもお伝えください。
まとめ
咽頭痛はのどの違和感程度の軽度のものから、唾液が飲み込めなくなる重度のものまで症状の程度はさまざまです。
咽頭痛の原因は風邪や急性咽頭炎がほとんどですが、ごくまれに腫瘍や他の病気が隠れているケースなどがあります。
なかなか咽頭痛が改善しない、徐々に症状がひどくなる、ご飯も満足に食べられないなどのケースでは、積極的に医師の診断・治療を受けることをおすすめします。
つくば市の内科B-leafメディカル内科小児科クリニックまでお気軽にご相談ください。

つくば市の内科 B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。
ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でもつくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックにお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
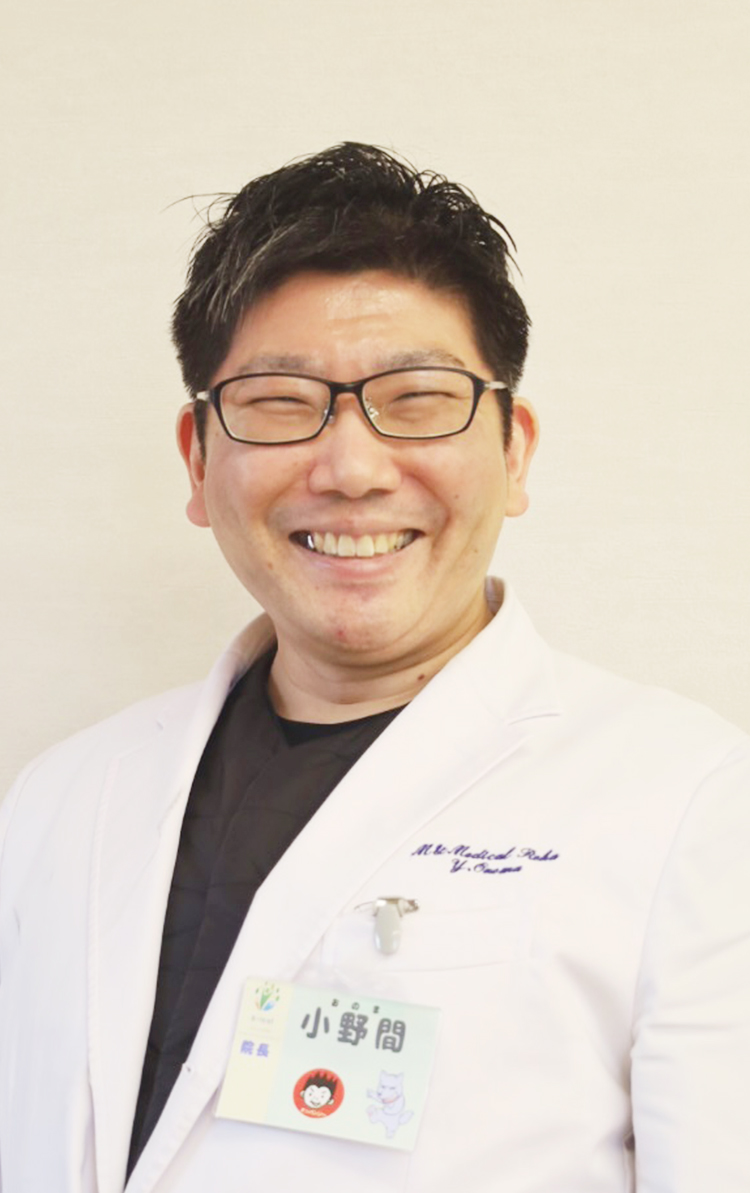
小野間 優介(おのま ゆうすけ)
B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長
- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得
- 日本医師会認定産業医
- 茨城県難病指定医
- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
--プロフィール--
2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、
『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』
『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』
をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。
関連リンク
- 病名から探す
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症

- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症