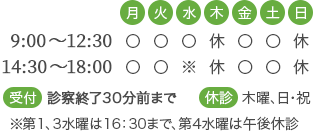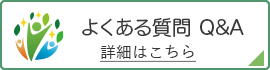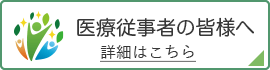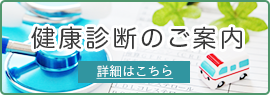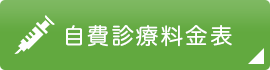RSウイルス感染症は、例年、夏の終わりごろから流行が始まり、年末ごろまで続く呼吸器感染症です。
近年では夏に流行が見られることもあり、一年を通じて注意したい病気です。
あまり聞きなじみのない言葉のRSウイルスの特徴や予防・治療法などの基本的知識について解説します。
RSウイルス感染症とは
「RSウイルス」に感染することでかかる呼吸器の感染症です。
また赤ちゃんが感染すると細気管支炎や肺炎などを起こす可能性が高くなります。
また、心臓や肺に基礎疾患がある場合や未熟児として生まれた場合は重症化のリスクがさらに高くなります。
しかしRSウイルスは日本を含めた世界で広く分布しており、何度も感染と発病を繰り返しますが、2歳になるまでにほとんどのこどもが1度はRSウイルスに感染すると言われていますので過度な心配をする必要はありません。
RSウイルスの症状
健康なこどもや大人が感染した場合は、ほとんどが軽い風邪のような症状となります。
しかし生後数週間~数か月の乳幼児が初めて感染した場合は重症化しやすいと言われているので、注意が必要になります。
感染後2~8日の潜伏期間のあと、発熱や鼻水、咳などのいわゆる風邪症状が2~3日続きます。
この期間で多くの場合は治っていきますが、重症化すると、喘鳴(ヒューヒュー・ゼーゼーなど)を伴う咳や呼吸困難になることがあります。
そこから細気管支炎や肺炎へと悪化していきます。
特に乳幼児の初めての感染時の約7割は、前述のように軽い症状で数日のうちに治っていきますが、残りの約3割は喘鳴や息苦しい様子や呼吸困難など、重大な症状を起こすことがあります。
そのため生後2~3カ月未満のこどもがRSウイルスに感染したときは、注意が必要です。
つくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックでも診断治療を行っております。お気軽にご相談ください。
RSウイルスの感染の経路と予防方法
感染経路は空気感染ではなく、くしゃみや咳、会話の時に飛ぶしぶきなどを吸い込む「飛沫感染」とおもちゃや食器などを触り、その手をなめたりすることで起きる「接触感染」です。
そのため、手洗いうがいの徹底、おもちゃやコップなどよく触るものの消毒が非常に有効な予防法です。
患者のほとんどは乳幼児~2歳児となります。
大人も感染はしていますが、気づいていないケースがほとんどです。
そのため、0~2歳の乳幼児の近くで話す際などはマスクの着用やこまめなアルコール消毒など感染対策をとる事が非常に大切です。
RSウイルスの診断・治療方法
鼻水の検査を行うことで感染の判断をします。
治療法は症状を緩和していく対症療法が中心となります。
解熱剤も発熱により衰弱してしまったり、眠れなかったりなどの場合に使用します。
多くは対症療法で治っていきますが、場合によっては点滴や入院での治療が必要になります。
RSウイルスに感染した場合の登園・登校について
RSウイルスは「何日休まなければならない」というはっきりとした基準はありません。
ただし、幼稚園や保育園で独自に登園停止を定めているケースもあるため、その場合は園のルールに則ってお休みしてください。
先ほどもお伝えした通り、飛沫感染することもあるため、咳が続く、熱があるなど調子が悪い場合には、登園は控えることをおすすめします。
発熱が収まり、体調が良くなれば登園・登校しても大丈夫です。
まとめ
RSウイルスは、毎年流行し、健康なこどもや大人は感染した場合は軽い風邪症状を発症します。
乳幼児や持病がある人は、重症化する割合は多くなりますので注意してください。
発熱や咳などが出た場合はRSウイルス感染症やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の可能性がありますので、発熱外来を受診しましょう。
つくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックでも発熱外来を行っております。お気軽にお問い合わせください。

つくば市の内科 B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。
ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でもつくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックにお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
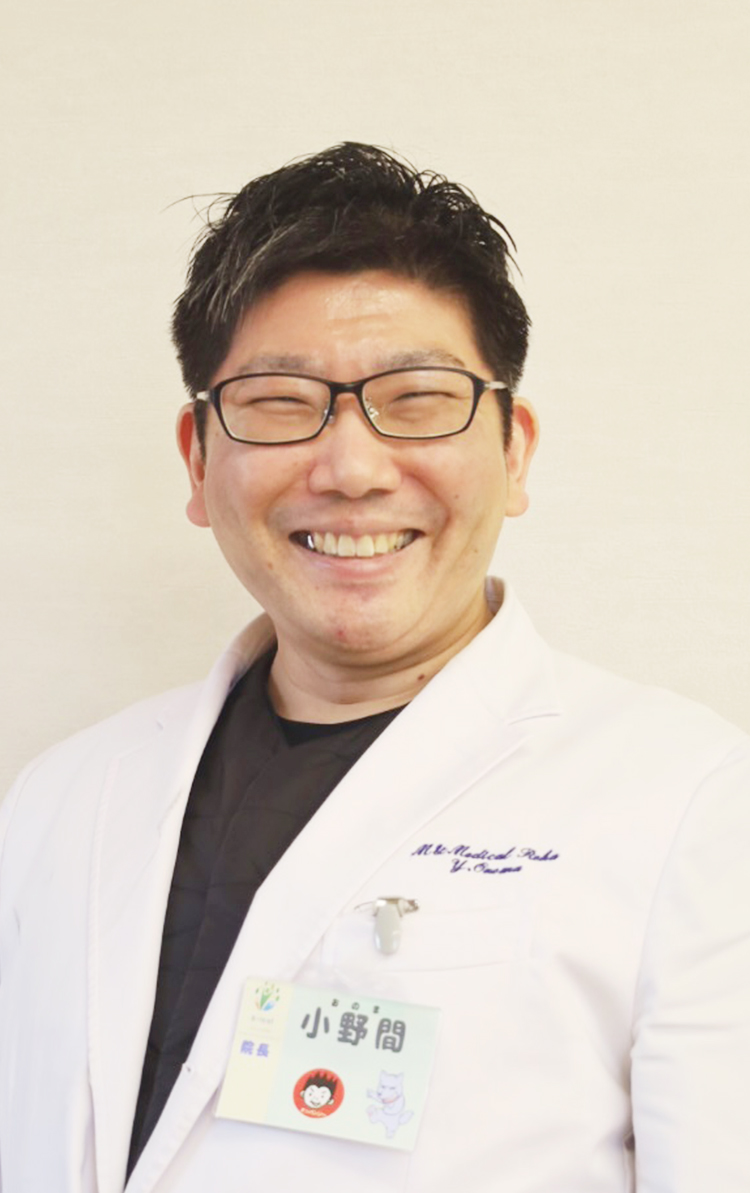
小野間 優介(おのま ゆうすけ)
B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長
- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得
- 日本医師会認定産業医
- 茨城県難病指定医
- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
--プロフィール--
2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、
『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』
『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』
をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。
関連リンク
- 病名から探す
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症

- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症