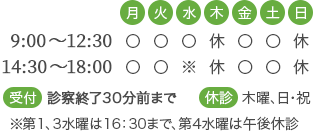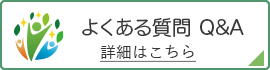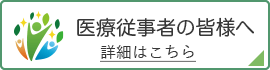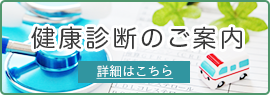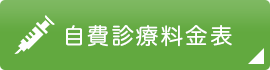ふるえには人前で緊張のためふるえる場合や、寒いときに出現する場合は問題ありませんが、コップをもったり箸を使ったりするときに出現するふるえは病気の可能性があります。
じっとしている(静止時)際に出現するふるえと、ある特定の動き(姿勢時)にふるえる場合があります。
静止時に出現する代表的な疾患がパーキンソン病です。
姿勢時のふるえは、水などの入ったコップで飲む時や、テレビを観ているときなどに出現することが多く、本態性振戦といわれる症状です。
本態性振戦は、ふるえ以外の症状はありません。
家族歴を認めることもあります。
本態性振戦の症状がひどい場合は、治療が必要になります。
内科の疾患では甲状腺機能亢進症による振幅の狭い、ふるえが多く出現します。
この他に、目標物に手を伸ばしたりする企図時や動作時に出現するふるえもあり、この場合は、小脳系の疾患の可能性があります。
慢性アルコール中毒などでも動作時に出現することがあります。
ふるえの出現する部位は、頭、口、手足、いずれの場合もあります。
声帯にふるえが出現する場合もあります。
静止時、姿勢時、企図時そして動作時にふるえが認められる場合は、受診する必要があります。
本態性振戦
とくに原因がなく、生理的なふるえが起こるような状況でもないのにもかかわらず、手や頭(首)にふるえが生じる病気です。
家族にも同様な症状が見られる場合もしばしば認められます。
- ふるえて文字がうまくかけない
- ふるえのせいでコップの水を飲むときにこぼしてしまう
- 食事のときに箸やスプーンを使いづらい
- 声もふるえてしまう
- 頭のふるえが気になる
- ふるえに気付かれたくなくて人に会うのが億劫になる
本態性振戦は、身体の一部が規則正しくリズミカルにふるえる神経系の疾患で、最も多くみられるのは手のふるえです。
また、頭、声、腕、脚にもふるえが起こる場合があります。
症状はふるえのみで、他の症状はありません。
高齢者のかなりの割合にみられ、40歳以上の25人に1人、65歳以上の5人に1人がかかるとされています。
発症の詳しい原因はまだよくわかっていませんが、緊張すると症状がひどくなり、加齢とともに進行するケースが多くみられます。
最近ではコンピューターのマウスの操作や銀行のATMの操作がふるえのためにうまくできないと訴える方も多く見受けられます。
パーキンソン病
多くは中年以降に発病します。
安静時に手足のふるえが起こるのが特徴で、その他にも筋肉のこわばりなどが見られ、歩行障害なども起こります。
本態性振戦と違って、手足のふるえは身体の左右どちらかに見られ、病気の進行に伴ってふるえが身体の両側に広がっていきます。
その他のふるえ
①生理的振戦
緊張した時や、力仕事をした後や運動した後などにふるえが見られます。
②甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
ふるえは、同じ姿勢をとり続けているときによく見られます。
ふるえの動く幅は狭く、ふるえの起こる頻度は高いです。
ふるえ以外に、動悸や息切れ、体重の減少、多汗などの症状が見られます。
③脳卒中(脳出血、脳梗塞)
急に起こった手足などのふるえなどに加え、ろれつが回らない、手に力が入らないといった症状が見られる場合は注意が必要です。
また、ガクガクとした痙攣発作が継続する場合も、脳が原因で起こっている可能性が高いので、すみやかに病院を受診することが大切です。
④アルコール依存症
⑤薬剤性振戦
気管支拡張剤や抗精神病薬、抗うつ薬、吐き気止め、めまい止めといった薬剤が原因で、手足にふるえが出ることがあります。
一般的に、原因となる薬剤を使用してから3から4ヶ月程度で症状が出ることが多く、薬剤性振戦が疑われる場合は、直ちに使用薬剤を停止する必要があります。
原因となる薬剤を中止すると症状が軽減する場合が多いですが、なかには症状が長期に渡って残る場合もあります。
⑥てんかん
てんかんとは、何らかの原因で、脳の神経細胞に異常な興奮が起こる病気で、「てんかん発作」と呼ばれる症状が見られます。
てんかん発作の中にはさまざまな種類があり、「手足がガクガクとふるえる」といったものから、「足を曲げたり伸ばしたりする」「手足の一部がピクッと痙攣する」といった発作があります。
本態性振戦とパーキンソン病の違い
| 本態性振戦 | パーキンソン病 | |
|---|---|---|
| 発症しやすい年齢 | 中高年に多いが、 若い人にも起きる | 中高年に多い |
| 家族歴 | しばしば見られる | 家族歴は少ないが、若年発症では家族歴を認める場合がある |
| ふるえが起きる部位 | 手(指先や腕)、足 頭(横に揺れる)、声 |
手、足 |
| ふるえの特徴 | 動作をしているときや、特定の姿勢をとったときにふるえが出る | 安静にしているときにふるえが強い |
| 書字について | 文字が上手に書けない 線が流れてしまう |
書いている文字が次第に小さくなる |
| その他の症状 | 声のふるえや、頭のふるえを伴う時もある | 筋肉のこわばり、動作緩慢、低血圧など多彩 |
| 病気の経過 | ほとんど進行しないか緩徐に進行する | 少しずつ進行する |
診察
ふるえや痙攣が起こる状況について詳しく問診をさせていただきます。
また、実際にふるえや痙攣が起こっている場合は、手足の状態などを詳しく視診してふるえや痙攣の状態を調べます。
気になる症状がある場合はつくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックまでご相談ください。
検査
MRI検査
MRI検査によって、ふるえや痙攣の原因が脳にあるかどうかを詳細に調べます。
脳波検査
ふるえや痙攣の状態によっては、脳波検査を行います。
脳波検査が必要な場合は提携病院を紹介いたします。
治療方法
お薬による治療
本態性振戦にはβ遮断薬という、高血圧や狭心症などの治療によく使用されている薬が処方されます。
この薬は交感神経のたかぶりを抑えるように作用しますが、その作用によって手指や首の筋肉への交感神経の刺激が和らげられて、ふるえが弱まると考えられています。
β遮断薬でふるえを十分に抑えられない場合や、β遮断薬を服用できない患者さんには、抗不安薬や抗てんかん薬などが処方されることもあります。
手術による治療
外科的治療には、「脳深部刺激療法」、「凝固療法」、「集束超音波治療」等いくつかの手術方法があります。
CHECK!
「ふるえ・痙攣」にはこんな症状があります
- 何もしていないのに手足が小刻みにふるえる
- 手足が勝手にピクっと動くことがある
- 字を書くときなどに手がふるえてうまく書けない
- 顔面がピクピクと痙攣する
- 手足がふるえ力が入りづらい

つくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。
ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でも つくば市のB-leafメディカル内科小児科クリニックまでお気軽にご相談ください。
参考資料
この記事の監修者
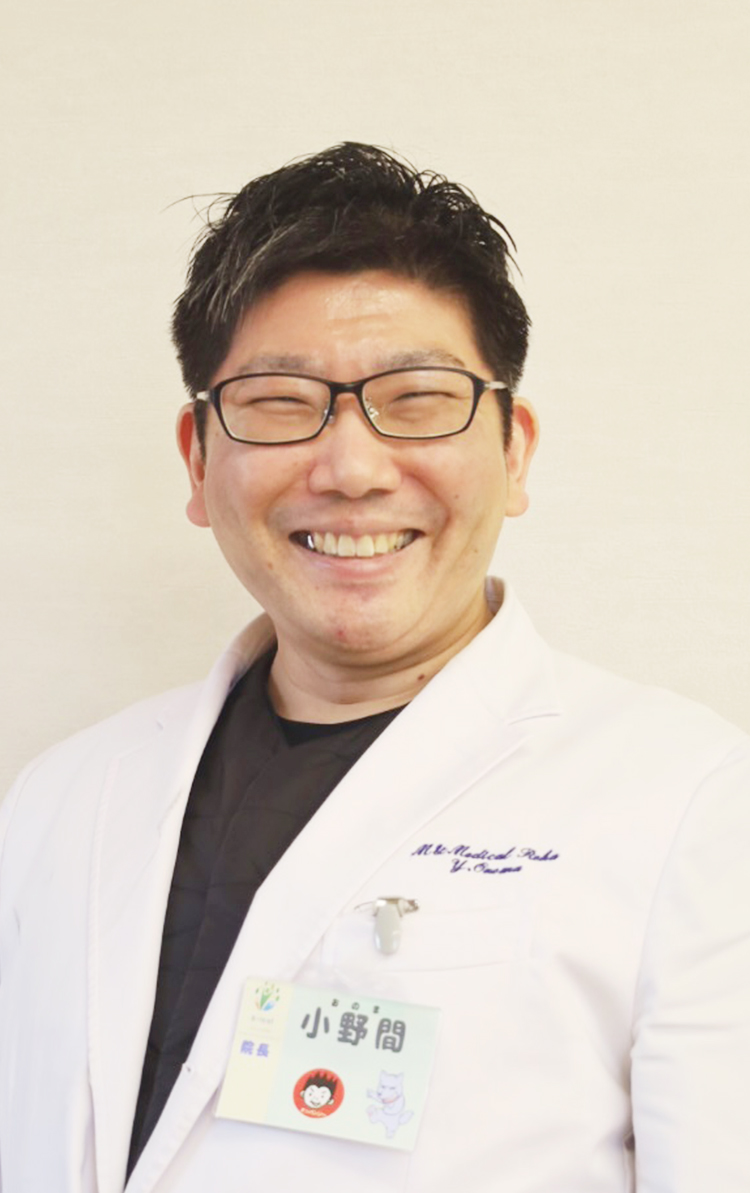
小野間 優介(おのま ゆうすけ)
B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長
- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得
- 日本医師会認定産業医
- 茨城県難病指定医
- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
--プロフィール--
2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、
『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』
『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』
をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。
関連リンク
- 病名から探す
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症

- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
- 認知症
- 脳血管障害(脳卒中)
- 一過性脳虚血発作(TIA)
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- パーキンソン病
- てんかん
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 帯状疱疹
- 帯状疱疹ワクチン
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症
- 気管支炎
- 気管支喘息
- 不整脈
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 膀胱炎
- 胃潰瘍
- 胃腸炎
- 甲状腺機能亢進症
- インフルエンザ
- 咽頭痛
- 子宮頸がん
- 子宮頸がんワクチン
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 手根管症候群
- ばね指
- 頸椎症
- RSウイルス感染症
- 溶連菌感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 水ぼうそう
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- アデノウイルス感染症
- 自律神経失調症